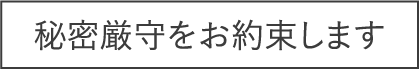離婚に関する住宅ローンの問題
~すぐに売却したいVSそのまま住み続けたい~
離婚に関する住宅ローンの問題は簡単に解決する事例がとても少ないです。なぜなら、夫と妻で意見が異なることが多いからです。
よくある事例として、お子様がいるご家庭では、夫は「すぐに家を売却してスッキリしたい」と考える一方で、妻は「子供を転校させたくないので住み続けたい」という場合です。
意見が対立することで、住宅ローン問題を後回しにしてしまうケースは多くあります。
離婚を検討されている場合は、住宅ローンについて事前に確認しておくべきことが3つあります。
離婚した後もそのまま住み続けるには?
①そのまま住宅ローンの返済を続けて住み続ける
元夫が順調に住宅ローンを払い続ける場合は何の問題もありません。
一方、元夫が住宅ローンを滞納してしまうと、突然、催促状や催告書が届く場合があります。競売の通知が突然届いた!という場合にはすぐに任意売却の手続きを始めましょう。
②リースバックを活用して住み続ける
リースバックとは、「自宅を第三者に売却したうえで、そのまま賃貸物件として借りて住み続ける」ということです。
ECエンタープライズではお客様のご希望で、リースバックを実行した事例もございます。
リースバックを行う際には、自宅を買い取ってくれる投資家を探す必要や賃貸の価格設定など、ご自身で交渉するには難しいところがございます。
そのため、「離婚した後も、そのご自宅に住み続けたい」と思ったときには、まずは専門家へ相談することをおすすめしております。
連帯保証人は解除できるのか?
解除できなかったら?
連帯保証人を外れるのは難しいです。連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済された時です。ローンを返済している途中である以上、連帯保証人を抜けることは極めて困難です。
それでも、どうしても連帯保証人を抜けたいという場合には、3つの方法があります。
-
住宅ローンの借り換え
現在の住宅ローン残債が、夫婦合計の収入ではなく夫一人の収入で借り換えることが可能なのであれば、妻が連帯保証人になる必要はありません。そのため離婚をする前にローンを借り換えて名義を夫一人にすることで、連帯保証の責任は消滅することになります。
-
代わりの人を連帯保証人として立てる
一定以上の収入のある人に、連帯保証を代わってもらうことです。 高額かつ長きに渡って返済していく必要がある、リスクの大きい住宅ローンの連帯保証人の代わりを探すのは、かなり親しい親族であっても難しいでしょう。
-
別の不動産を担保にする
住宅ローンに相当する一定以上の資産を持っている場合は、それを担保にして連帯保証人を解除する方法です。いざという時の担保があれば、金融機関も納得する場合が多いでしょう。

住宅ローンのオーバーローンとアンダーローン
離婚時に住宅ローンが残っている場合は、まずは自宅の評価と住宅ローンの差額を示す「オーバーローン」か「アンダーローン」かを調べる必要があります。
家の価値が住宅ローンの残額を上回っていてアンダーローン状態であれば、家は財産分与の対象になるため、その金額を2分割するのが一般的でしょう。
一方、ローン残額が家の価値より上回るオーバーローンだった場合、家を売ってもローンが残ることになるので通常の売却はできません。 そして離婚する夫婦の両方もしくは一方が、家のローンを完済するまで支払い続けることになります。 その場合、ローンの負担はどうするのか、名義はどうするか、財産分与はどうするのかなどの解決しなければいけない問題がたくさん発生します。
それでも不動産を売却したいと考えるなら、任意売却という方法があります。オーバーローンの場合は、専門家にアドバイスを求めましょう。


離婚時に持ち家をどうするか
困ったらまずはお気軽にご相談ください!
ご相談いただければ、住宅ローンの残債を調べたり、所有名義やローン名義、連帯保証人がどうなっているのかお調べさせていただきます。
また、同時に不動産の評価額を把握することで住宅ローンの返済が可能なのかどうかを一緒に考えさせていただきます。
1人で悩まずにEC.エンタープライズ無料相談窓口へいち早く相談を!!
トップページへ戻る